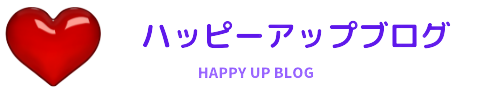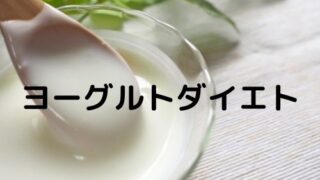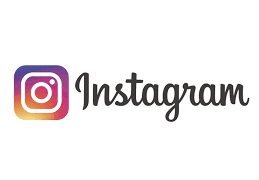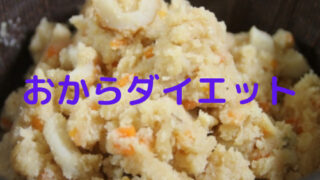七福神は一般的には、恵比寿(えびす)、大黒天(だいこくてん)、福禄寿(ふくろくじゅ)、毘沙門天(びしゃもんてん)、布袋(ほてい)、寿老人(じゅろうじん)、弁財天(べんざいてん)、とされております。

大黒天とは
大黒は梵語の摩訶迦羅 マハー・カーラ の訳です。
日本では、大黒の「だいこく」が大国に通じるため、古くから神道の神である大国主と混同され、習合して、当初は破壊と豊穣の神として信仰される。後に豊穣の面が残り、七福神の一柱の大黒様として知られる食物・財福を司る神となった。室町時代以降は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の民族的信仰と習合されて、微笑の相が加えられ、さらに江戸時代になると米俵に乗るといった現在よく知られる像容となった。現在においては一般には米俵に乗り福袋と打出の小槌を持った微笑の長者形で表される。(ウィキペディア Wikipediaより)


- 狩衣のような服を着て頭巾をかぶり、右手に打出の小槌、左手に大きな袋を背負い、米俵の上に立っているのが一般的です。
- 俵に乗っている由緒は「毎日ご飯を供えてお参りすれば、一生、食に不自由はさせない」というお告げあった話が残されており、米俵と結びついたようです。
- 食堂や台所にまつられることが多く、そこから転じて寺の婦人(僧侶の妻)を大黒さまと呼ぶこともあります。
- また建物の中心となる太い柱を大黒柱と呼びますが、これは大黒さまが天・地・人を守る事から屋台骨を支えるものをこのように呼びます。
- 金運良好 資産増加 厨房守護(食べ物に恵まれる)恋愛成就 夫婦和合 家内安全 家運隆昌 子孫繁栄等代表的福の神のご利益
恵比寿と大黒天

- 大黒と恵比寿は各々七福神の一柱であるが、寿老人と福禄寿が二柱で一組で信仰される事と同様に、一組で信仰されることが多い。神楽などでも恵比寿舞と大黒舞が夙(つと)に知られ、このことは大黒が五穀豊穣の農業の神である面と恵比寿が大漁追福の漁業の神である面に起因すると考えられている。また商業においても農産物や水産物は主力であったことから商売の神としても信仰されるようになっていった。
大黒天を祀る神社・寺院

寺院
- 大黒寺(大阪府羽曳野市) – 日本最初大黒天出現霊場
- 大黒寺(京都市伏見区)
- 大円寺 (目黒区)(東京都)-元祖山手七福神
- 浅草寺(東京都台東区) – 米びつ大黒/浅草名所七福神
- 寛永寺護国院(東京都台東区) –谷中七福神
- 鬼子母神(東京都豊島区) – 大黒堂/雑司が谷七福神[5]
- 本光寺(千葉県市川市) – 金大黒天
神社
- 日本一大きいえびす、大黒の石像は舞子六神社(兵庫県神戸市)
- 神田明神(東京都千代田区)
- 大前神社(栃木県真岡市)
- 敷津松之宮大国主神社(大阪府大阪市) – 日之出大国/浪華七福神
- 春日大社摂社夫婦大國社(奈良県奈良市) – 夫婦大黒天像(6年に1度御前立開帳)
『ウィキペディア(Wikipedia)より』
参考動画(ユーチューブより)
大国主命と大黒天様は 同じ神様?

大黒天
大黒天のこと、分かってくれたかな?これからも宜しく!
皆さんをハッピーアップしますよ!!